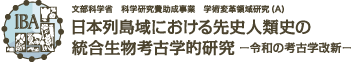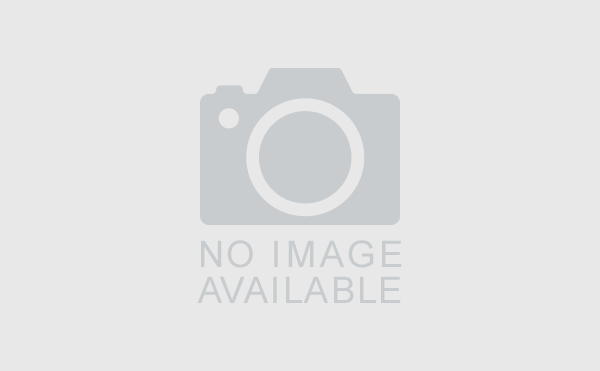C03班の那須先生のご研究が、PNASに掲載されました。
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2510835122
今回、中国の黄河流域で9000年前頃のアズキの炭化種子が見つかり、アワ・キビ・イネを伴うことから、アズキも、雑穀やイネと同様に栽培されていた可能性が示されました。さらに、中国、韓国、日本で出土したアズキのサイズの時系列変化を調べたところ、4000年前頃までには各地でそれぞれ種子サイズの大型化が見られ、各地で独自に栽培植物化が進んでいたことが明らかになりました。
このことは、アズキが東アジアのどこかひとつの地域で進化したのではなく、各地で多元的に進化していた可能性を示唆します。ただし、進化の過程には地域差が見られ、中国や韓国よりも日本のアズキの方が急激に大型化しており、当時の環境条件と食文化が影響した可能性が指摘出来ました。
先行研究であるC03班の内藤先生らの遺伝学的研究の結果では、アズキの日本起源を示していますが、この結果と統合すると、3000年前以降のどこかの時点で日本のアズキが大陸に伝わり、日本の赤くて大きいアズキが大陸でも好まれたため広まり、現在は日本起源のアズキしか栽培されなくなったと考えることができます。
統合生物考古学的にも、非常に興味深い研究成果となりました。